「電子帳簿保存法ってなに?自社は対応する必要があるの?」
「電子取引のデータ保存が義務化されたって聞いたけど、どうすればいいの?」
「電子帳簿保存法に対応するメリットは?具体的な対応方法は?」
2024年1月から電子取引データの保存が完全義務化され、多くの経理担当者や事業者が対応に追われているのではないでしょうか。
実際、電子帳簿保存法への不適切な対応は青色申告の取り消しや税務調査の長期化など、事業運営に大きな影響を及ぼす危険性があります。
そのような悩みを解決するためには、電子帳簿保存法に関する正しい知識と事前の準備が不可欠です。
本記事では、2025年の最新情報を踏まえて電子帳簿保存法の基本から具体的な対応方法まで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、電子帳簿保存法の正しい知識と準備のステップを理解でき適切な対応ができるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。
電子帳簿保存法とは?基本をわかりやすく解説
電子帳簿保存法の義務化について知っていても、その詳細や実務への影響を把握できていない方も多いのではないでしょうか。
電子帳簿保存法とは国税関係帳簿書類の電子的保存に関する法律で、以下のように定義されています。
正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。
納税者が国税に関わる帳簿や書類を電子データで作成・保存する際の要件や手続きを定めた法律です。
この法律により、一定の要件を満たせば紙での保存義務が免除され、電子データのみでの保存が認められています。
本章では、電子帳簿保存法に関する以下の内容について解説します。
・電子帳簿保存法の目的と背景
・電子帳簿保存法の3つの保存区分
・2024年改正のポイント
これらの内容を理解することで、電子帳簿保存法の全体像を把握して具体的な対応策の検討が可能です。
それぞれの項目について、以下で詳しく見ていきましょう。
電子帳簿保存法の目的と背景
電子帳簿保存法は1998年に施行された、国税関係書類の電子保存を認める法律です。
社会のデジタル化に対応し、企業の業務効率化とペーパーレス化を推進するために制定されました。
電子帳簿保存法の主な目的は、以下のとおりです。
- 書類保管スペースの大幅な削減
- 経理業務の効率化・時間短縮
- 企業全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進
- ペーパーレス化による環境負荷の軽減
当初は紙での保存が原則でしたが時代の変化に合わせて段階的に法改正が行われており、電子データでの保存範囲は年々拡大しています。
電子帳簿保存法の3つの保存区分
電子帳簿保存法には、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの区分があります。
書類の作成方法や受取方法によって保存方法が異なるため、それぞれに適した保存区分が設けられているのです。
それぞれの保存区分について、以下で詳しく解説します。
| 保存区分 | 対応義務 | 対象となる書類 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 任意 | 電子的に作成した帳簿・書類 | 会計ソフトで作成した帳簿 パソコンで作成した請求書の控え |
| スキャナ保存 | 任意 | 紙で受領・発行した書類 | 取引先から受け取った紙の請求書 紙の契約書をスキャンしたデータ |
| 電子取引データ保存 | 義務 | 電子的に授受した取引情報 | メールで受信したPDF請求書 クラウドからダウンロードした領収書 |
2024年1月より、3つの区分のうち電子取引データ保存が完全義務化されており、すべての事業者が対応しなければなりません。
電子帳簿等保存とスキャナ保存は任意ですが、業務効率化やペーパーレス推進のためにも導入を検討する価値があるでしょう。
2024年改正のポイント
2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正が施行され、電子取引データの電子保存が完全義務化されました。
デジタル化の促進と事業者の実態に合わせて法整備を進めるため、完全義務化と同時に一部要件の緩和や対象範囲の拡大が行われています。
2024年改正の主な変更点は、以下の3つです。
| 改正ポイント | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 電子取引データ保存の完全義務化 | 2024年1月1日より実施 | ・経過措置が2023年12月31日で終了 ・電子データを紙印刷での保存は原則不可 ・一定条件下では猶予措置あり |
| スキャナ保存要件の大幅緩和 | 実務負担の軽減 | ・解像度・階調情報の保存義務廃止 ・ 入力者等情報の確認要件廃止 ・帳簿との相互関連性確保は「重要書類」のみに限定 |
| 検索要件免除の対象拡大 | 適用範囲の拡大 | ・売上高基準が「1,000万円以下」から「5,000万円以下」に拡大 ・より多くの中小企業が検索要件の免除対象 |
2024年の改正では電子取引データの電子保存が義務化される一方で、企業規模や実務上の負担を考慮した緩和措置が導入されています。
小規模事業者へ配慮されているため、自社の状況に合わせた適切な対応方法を選択することが重要です。
電子帳簿保存法対応のメリットとデメリット
電子帳簿保存法への対応を検討する際、自社に適した導入方法を選択するためにはそのメリットとデメリットを理解しなければなりません。
本章では、対応によって得られる具体的なメリットと導入時の課題・解決策について詳しく解説します。
・対応することで得られる7つのメリット
・導入時の課題と解決策
それぞれのポイントを理解することで、電子帳簿保存法への対応をスムーズに進めて業務効率化やコスト削減を実現できるでしょう。
それぞれの項目について、以下で詳しく解説します。
対応することで得られる7つのメリット
電子帳簿保存法に対応することで、業務効率化からコスト削減まで様々なメリットが得られます。
デジタル化により、これまでの紙ベースの帳簿・書類管理における物理的・時間的制約が解消され、企業活動全体の最適化ができるためです。
以下で、電子帳簿保存法に対応することで得られる7つのメリット見ていきましょう。
| メリット | 内容 | 具体的効果 |
|---|---|---|
| 保管スペースの削減 | 紙の帳簿・書類の物理的保管は不要 | ・7年間の法定保存期間でも省スペース ・オフィススペースの有効活用が可能 |
| 検索・参照の効率化 | 必要な書類を即座に検索可能 | ・書類探しの時間を大幅削減 ・過去の取引データへの即時アクセス |
| 業務プロセスの効率化 | 書類受取から保管までの手間を削減 | ・経理担当者の業務負担軽減 ・高付加価値業務への時間再配分 |
| テレワーク対応 | リモートからのデータアクセスが可能 | ・場所を選ばない働き方の実現 ・出社しなくても経理業務の継続が可能 |
| コスト削減 | 紙関連の様々なコストを削減 | ・印刷コスト・郵送費・保管費用の削減 ・長期的な大幅コスト削減効果 |
| 環境負荷の軽減 | 紙使用量の減少による環境保全 | ・企業のSDGs活動としても評価 ・環境に配慮した経営姿勢のアピール |
| 税務上の優遇措置 | 「優良な電子帳簿」による特典 | ・過少申告加算税の5%軽減 ・青色申告特別控除(65万円)の要件充足 |
電子帳簿保存法への対応には法令遵守以上の価値があり、企業の業務効率化と経営基盤強化に直結します。
導入初期のコストや手間を考慮しても、中長期的には企業競争力向上に貢献する重要な経営戦略と位置づけられるでしょう。
導入時の課題と解決策
電子帳簿保存法の対応には、初期投資やワークフロー変更などの課題があり適切な対策をとらなければなりません。
新しい仕組みを導入する際には必ず障壁がありますが、段階的アプローチや適切なツール選定によって負担を最小化できます。
電子帳簿保存法の対応への課題と解決策は、以下のとおりです。
| 課題 | 解決法 | 参考ポイント |
|---|---|---|
| 初期コスト | ・企業規模に合ったシステム選定 ・無料/低コストのクラウドサービス活用 ・段階的な導入計画 | 中小企業向けに月額数千円からの クラウドサービスも多数存在 |
| 業務フロー変更の負担 | ・詳細なマニュアル整備 ・事前教育の実施 ・担当者へのサポート体制構築 | 優先度の高い書類から 段階的に移行するのが効果的 |
| システム対応の継続 | ・自動アップデート機能があるクラウドサービスの利用 ・税理士や専門家との連携 ・情報収集体制の整備 | 法改正情報は国税庁HPで 定期的にチェック |
| セキュリティリスク | ・適切なセキュリティ対策 ・アクセス権限の厳格な設定 ・定期的なバックアップ ・信頼性の高いクラウドサービスの活用 | データの定期バックアップは 必須の対策 |
電子帳簿保存法対応の課題は、事前の計画と適切なツール選択により効果的に解決できます。
特に中小企業では、自社の規模や業務特性に合わせたシンプルな対応から始めて段階的に拡充していく方法が現実的でしょう。
電子帳簿保存法の対象者と対象書類
電子帳簿保存法への対応にあたり自社が対応すべき内容を明確にするため、適用範囲を正確に理解することが不可欠です。
本章では、対象となる事業者の範囲と保存区分ごとの対象書類について詳しく解説します。
・対象となる事業者
・対象外となる事業者
・区分別の対象書類一覧
これらの情報を理解することで、自社の状況に合わせた適切な対応計画の立案が可能です。
それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
対象となる事業者
電子帳簿保存法は、所得税または法人税の申告義務がある事業者すべてに適用されます。
国税関係帳簿書類の保存義務がある納税者に対して電子データによる保存方法を定めた法律であることから、課税対象となる事業活動を行うすべての事業者が対象です。
対象となる事業者について、以下で見てみましょう。
| 区分 | 対象となる事業者 |
|---|---|
| 法人 | 株式会社・合同会社・公益法人・NPO法人・外国法人の日本支店 |
| 個人事業主 | 青色申告者・白色申告者 |
| 副業・兼業者 | 株式会社・合同会社・公益法人・NPO法人・外国法人の日本支店 |
企業の規模や業種に関わらず、電子取引を1件でも行っている事業者は電子帳簿保存法の対応が必要です。
法人になったばかりの小規模企業や個人事業主も対象であるため、早めに対応方法を検討しましょう。
対象外となる事業者
電子取引を一切行っていない事業者のみ、電子取引データ保存の対象外です。
電子取引データ保存は、電子的に授受した取引情報の適切な保存を義務付けるものであるため、そもそも電子取引を全く行っていない場合には対応義務が発生しません。
現代のビジネス環境では以下の取引だけでも「電子取引」に該当するため、完全に対象外となる事業者は極めて稀です。
- インターネットバンキングの利用
- クレジットカード決済の利用
- スマートフォンアプリでの決済
- 電子メールでの請求書PDF受領
- クラウドサービスでの見積書授受
実質的には、ほとんどすべての事業者が電子取引データ保存の対象となると考えるべきでしょう。
紙のみでの取引を徹底している場合を除き、何らかの電子取引が発生している可能性が高いため自社の取引状況を詳細に確認することが重要です。
区分別の対象書類一覧
電子帳簿保存法の3つの区分では、それぞれ異なる種類の書類が対象です。
書類の作成方法や受取形態によって保存方法が異なるため、帳簿・書類の特性に応じた保存区分と要件が設けられています。
それぞれの保存区分に対する書類の種類は、以下のとおりです。
| 保存区分 | 主な対象書類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 【任意】 | 国税関係帳簿 決算関係書類 取引関係書類の控え | 仕訳帳・総勘定元帳・売掛帳・買掛帳 現金出納帳・固定資産台帳・その他補助簿 貸借対照表・損益計算書 棚卸表・試算表 請求書・見積書・納品書の控え 契約書・領収書の控え |
| スキャナ保存 【任意】 | 重要書類 (資金や物の流れに直結) 一般書類 (資金や物の流れに直結しない) | 契約書・請求書・領収書・納品書 預り証・借用証書 見積書・注文書 検収書・入庫報告書 |
| 電子取引データ保存 【義務】 | 電子的に授受した取引情報 | メール添付PDFの請求書や領収書 クラウドサービス経由の見積書や契約書 ECサイトの購入履歴や領収書 クレジットカードの利用明細データ インターネットバンキングの取引明細 スマートフォンアプリによる決済データ |
対象書類は各区分によって明確に分かれており、特に「電子取引データ保存」は電子でやり取りするあらゆる取引情報が対象となるため注意しましょう。
自社で扱っている書類を区分ごとに整理し、それぞれの保存要件に則った対応を計画的に進めることが法令遵守の第一歩です。
電子帳簿保存法の保存要件
電子帳簿保存法の保存要件は、正しく理解したうえで適切に対応しなければ法令違反となるリスクがあります。
本章では、3つの区分それぞれの保存要件について詳しく解説します。
・電子帳簿等保存の要件
・スキャナ保存の要件
・電子取引データ保存の要件
各区分の要件を正確に理解することで、自社の状況に合わせた効率的な対応が可能です。
それぞれの区分の要件について、詳しく見ていきましょう。
電子帳簿等保存の要件
電子帳簿等保存には「優良な電子帳簿」と「一般電子帳簿」の2種類があり、それぞれ満たすべき要件が異なります。
より高い信頼性と透明性を確保した「優良な電子帳簿」には税務上の優遇措置が与えられるため、厳しい要件が設定されています。
以下で、それぞれの種類に対する要件を見てみましょう。
| 区分 | 要件 | 詳細 |
|---|---|---|
| 優良な電子帳簿の要件 (すべて満たす必要あり) | 訂正・削除履歴の確認 | 帳簿の記録内容の訂正・削除履歴が残るシステムを使用 |
| 業務処理期間後の入力確認 | 通常期間(2ヶ月以内)を過ぎた入力はその事実が確認できる | |
| 帳簿間の相互関連性確保 | 総勘定元帳と仕訳帳などの間でデータの関連性を確認可能 | |
| システム関係書類の備付 | システムの概要書や操作マニュアルを保管 | |
| 見読可能性の確保 | ディスプレイやプリンタでデータを閲覧・印刷可能 | |
| 検索機能の確保 | 取引年月日・金額・取引先での検索 日付・金額の範囲指定検索 複数条件を組み合わせた検索 | |
| 一般電子帳簿の要件 (最低限の要件) | システム関係書類の備付 | システムの概要書や操作マニュアルを保管 |
| 見読可能性の確保 | ディスプレイやプリンタでデータを閲覧・印刷可能 | |
| 税務調査時のデータ提供 | 税務調査時にデータのダウンロード等の求めに応じられる |
「優良な電子帳簿」として認められると過少申告加算税が5%軽減されるほか、個人事業主は青色申告特別控除の要件も満たせるメリットがあります。
会計ソフトの多くは「優良な電子帳簿」の要件を満たせるよう設計されているため、ソフト選定時にはこの点を確認することが重要です。
スキャナ保存の要件
スキャナ保存の要件は、「重要書類」と「一般書類」で異なり、適切な解像度やタイムスタンプなどの技術的要件を満たす必要があります。
紙の原本を廃棄しても電子データが証拠として認められるためには、改ざん防止や原本の忠実な再現性を担保する措置が不可欠なためです。
以下では、具体的なスキャナ保存の要件について見ていきましょう。
| 要件区分 | 重要書類 | 一般書類 |
|---|---|---|
| 対象書類例 | 契約書・請求書・領収書・納品書など | 見積書・注文書・検収書など |
| 共通要件 | 解像度200dpi以上で読取 タイムスタンプ付与または訂正削除履歴が残るシステム システム関係書類の備付 見読可能性の確保 検索機能の確保 | 同左 |
| カラー要件 | カラーで読取必須 (赤・緑・青が各256階調以上) | グレースケール(白黒)でも可能 |
| 入力期間要件 | 受領後7営業日以内 または業務サイクル後 (最長2か月+7営業日以内) | 入力期間の制限なし |
| 帳簿関連性要件 | 帳簿との相互関連性確保が必要 | 帳簿との相互関連性不要 |
スキャナ保存は技術的要件が多いため、実務的には専用のシステムやサービスを利用することが効率的といえます。
重要書類と一般書類で要件が異なる点に注意し、入力期間やカラースキャンなどの要件を確実に満たす運用体制を構築することが必要です。
電子取引データ保存の要件
電子取引データ保存には「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの要件があり、2024年から義務化されたため確実な対応が必要です。
電子データは改ざんが容易なため、データの信頼性を担保する仕組みと必要時に迅速に確認・検索できる環境の整備が求められます。
具体的な要件区分は、以下のとおりです。
| 要件区分 | 内容 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 真実性の確保 (いずれか1つを選択) | タイムスタンプの活用 | タイムスタンプ付きデータを受領 データ受領後、速やかにタイムスタンプを付与 |
| システムによる改ざん防止 | 訂正・削除履歴が残るシステムを使用 訂正・削除できないシステムを使用 | |
| 事務処理規程による運用 | 訂正・削除防止に関する事務処理規程を策定 規程に従った適切な運用を実施 | |
| 可視性の確保 | システム関係書類の備付 | システムの説明書やマニュアルを保管 |
| 見読可能性の確保 | 電子データを画面や紙で確認できる環境整備 | |
| 検索機能の確保 ※ | 取引年月日、取引金額、取引先での検索 日付・金額の範囲指定検索 複数条件を組み合わせた検索 |
※ 売上高5,000万円以下の事業者や、電子取引データを印刷して整理保存している事業者は、検索機能要件が免除されます。
電子取引データ保存は2024年から完全義務化されたため、すべての事業者が何らかの対応を行う必要があります。
小規模事業者には要件緩和措置もあるため、自社の状況に合わせた対応を選択することが重要です。
実践!電子帳簿保存法への対応方法
電子帳簿保存法に適切に対応するためには、自社の業務状況を正確に把握して計画的に準備を進めることが重要です。
本章では、電子帳簿保存法の対応に向けた具体的なステップを解説します。
・自社の現状確認と必要な対応の見極め方
・電子帳簿等保存への具体的な対応ステップ
・スキャナ保存への具体的な対応ステップ
・電子取引データ保存への具体的な対応ステップ
これらのステップを理解することで、自社に最適な電子帳簿保存法対応をスムーズに進めることができます。
それでは各ステップについて、詳しく見ていきましょう。
自社の現状確認と必要な対応の見極め方
電子帳簿保存法への対応は、まず自社の現状を正確に把握してどの区分の対応が必要かを見極めることから始めましょう。
各企業ごとに取引形態や書類の授受方法は異なり、自社に関係のない部分まで対応すると無駄なコストや労力が発生してしまうからです。
以下の4つのステップで自社の現状を確認してみましょう。
まずは、電子取引の有無について確認します。
- メールで請求書・見積書などをやり取り
- クラウドサービスで取引書類をやり取り
- ECサイトでの購入履歴・領収書あり
- クレジットカード明細・ネットバンキング利用
これらの項目に該当する場合は、電子取引データ保存が必要です。
次に、対象となる書類を洗い出します。
- 取り扱っている国税関係書類の種類を整理
- 各書類の授受形態(紙・電子)を確認
- 月間・年間の取引量を把握
この作業で、どの書類を電子取引データとして保存すべきかがわかりました。
続いて、洗い出した書類の現在の保存状態を確認します。
- 紙保存:ファイリング方法・保管場所・検索方法
- 電子保存:保存場所・ファイル形式・バックアップ体制
これで現状が整理できました。
最後に、電子取引データ保存対応の優先度を決めます。
- 電子取引データ保存が義務化されている書類
- 取引量の多い書類
- 任意の書類(余裕があれば)
自社の現状を正確に把握することで、無駄のない効率的な対応計画を立てることができます。
まずは電子取引データ保存の対応を優先し、その後リソースに応じて電子帳簿等保存やスキャナ保存の対応を検討するとよいでしょう。
電子帳簿等保存への具体的な対応ステップ
電子帳簿等保存は任意の対応区分ですが、適切に対応することで業務効率化や税務メリットが得られます。
帳簿類を電子データで保存すれば、紙への出力・保管コストが削減でき「優良な電子帳簿」として認められて税務上の優遇措置を受けることが可能です。
電子帳簿等保存への対応は、以下の4ステップで進めましょう。
以下の点を確認して適切なシステムを選びましょう。
- 電子帳簿保存法への対応表明があるか
- 「優良な電子帳簿」の要件を満たせるか
- 自社の業務規模・特性に合っているか
具体的なおすすめは、以下の会計ソフトです。
| おすすめ会計ソフト | 特徴 |
|---|---|
| freee会計 | クラウド型・操作性が良い・自動連携機能充実 |
| マネーフォワード クラウド | 多機能・他サービスとの連携性高い |
| 弥生会計 | 老舗・安定性高い・導入実績多数 |
これで要件を満たすシステムの候補が見つかりました。
次に、電子保存のための具体的な運用ルールを策定します。
- データ入力から保存までの流れを明確化
- 担当者・責任者の役割と権限を定義
- 訂正・削除が必要な場合の承認フローを設計
これで電子帳簿等保存の日常業務の流れが整理できました。
続いて、保存要件を満たすための環境を整えます。
- システム関係書類(操作マニュアル等)の準備
- 必要機器(ディスプレイ・プリンタ等)の設置
- データバックアップ体制の構築
- アクセス権限の設定
これで電子保存に必要な環境が整いました。
最後に、税務上の優遇措置を受けるための手続きを行います。
- 「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を準備
- 法定申告期限までに管轄の税務署に提出
- 届出書の控えを保管
これですべての準備と手続きが完了しました。
電子帳簿等保存は適切なシステム選定と運用設計が重要であり、「優良な電子帳簿」認定で得られるメリットのためにも要件を満たす準備が不可欠です。
スキャナ保存への具体的な対応ステップ
スキャナ保存は紙の書類を電子化して保存できる任意の制度ですが、適切に対応すれば原本の破棄が可能となり保管スペースの大幅削減につながります。
紙保管が不要になるとスペース削減だけでなく検索性向上や業務効率化もできますが、そのためには法定要件を満たす環境と運用体制の構築が必要です。
スキャナ保存への対応は、以下の4ステップで進めましょう。
まずは、スキャナ保存の技術的要件を満たす機器を準備します。
- 解像度200dpi以上でカラー対応のスキャナまたはスマートフォン
- 14インチ以上のカラーディスプレイ
- カラープリンタ
- データ保存用のストレージ環境
これで法定要件を満たす機器環境が整いました。
次に、真実性確保のためのタイムスタンプ対応を準備します。
- タイムスタンプサービスの導入
- 訂正・削除履歴が残るシステムの導入
| おすすめタイムスタンプサービス | 特徴 |
|---|---|
| GMOグローバルサイン タイムスタンプ | 大手・多数の導入実績・安定性高い |
| セコムタイムスタンプサービス | 信頼性高い・長期保存対応 |
| アマノタイムスタンプサービス | 使いやすい・中小企業向けプランあり |
これで真実性確保のための準備ができました。
続いて、スキャナ保存の運用ルールを整備します。
- スキャン担当者と承認者の指定
- スキャン・保存の期限設定(重要書類は受領後7営業日以内など)
- スキャン後の原本の取扱いルール(保管期間・廃棄方法など)
- 例外対応の手順(大型書類・汚損書類など)
これでスキャナ保存の日常業務の流れが整理できました。
最後に、電子保存したデータの検索環境を整備します。
- 取引年月日、取引金額、取引先で検索できる仕組みの導入
- ファイル名の付け方のルール化(例:YYYYMMDD_金額_取引先名.pdf)
- インデックスデータの作成
- フォルダ構成の設計(年月・取引先別など)
これで必要なときに素早く書類を探せる環境が整いました。
厳格な要件が課される重要書類については、システムや専門家の力を借りて確実に法的要件を満たす体制構築が必要です。
電子取引データ保存への具体的な対応ステップ
電子取引データ保存は2024年から完全義務化された区分であり、すべての事業者が適切に対応する必要があります。
メールやクラウドサービスを介して受け取った情報は、真実性と可視性を確保した上で電子データのまま保存することが義務付けられているからです。
電子取引データ保存への対応は、以下の4ステップで進めましょう。
まずは、データの真実性を確保する方法を選択します。
| 方法 | 具体的な対応 | 適した企業規模 |
|---|---|---|
| タイムスタンプ利用 | タイムスタンプサービス契約 受領データへの付与ルール策定 | 中小企業 |
| 専用システム導入 | 電子帳簿保存法対応システム選定 訂正・削除履歴管理機能確認 | 中堅〜大企業 |
| クラウドサービス活用 | 改ざん防止機能付きストレージ利用 適切なアクセス権限設定 | 小〜中規模企業 |
| 事務処理規程整備 | 国税庁サンプル参考に規程作成 社内周知と運用徹底 | 小規模企業 |
これで真実性確保の方法が決まりました。
次に、電子取引データの保存環境を整えます。
- 社内サーバー:セキュリティ管理が容易だがコスト高
- クラウドストレージ:コスト低いが選定に注意
- 専用システム:機能充実だが導入コスト考慮
- 名称規則:「YYYYMMDD_金額_取引先名.pdf」
- フォルダ構成:年月/取引先/取引種類など
- バックアップ頻度:日次または週次
これでデータ保存環境の設計ができました。
続いて、保存データの検索機能を確保します。
- ファイル名による検索:日付・金額・取引先含む命名規則
- 検索用台帳作成:Excel等で取引リスト作成
- フォルダ整理:取引年月日・取引先別に構造化
- 前々年/前々事業年度の売上高が5,000万円以下
- 電子取引データを印刷して整理保存している
これで必要なデータをすぐに検索できる環境が整いました。
最後に、日常的な運用ルールを整備します。
- 電子データ受領時の保存手順(担当者・タイミング)
- データ保存の責任者と権限設定
- 保存期間(原則7年間)の管理方法
- システム障害・例外時の対応方法
- マニュアル作成と配布
- 定期的な研修実施
- 運用状況の定期チェック体制
これですべての準備と体制が整いました。
電子取引データ保存は義務のため小規模企業は事務処理規程から始めて、自社の状況に合った対応方法と運用体制の整備が不可欠です。
電子帳簿保存法に関するよくある誤解と質問
電子帳簿保存法に対する理解が不十分の場合、必要以上の対応や対応不足によるリスクが生じる危険性があるため注意が必要です。
本章では、電子帳簿保存法をめぐる誤解や対応しない場合のリスク、小規模事業者向けの緩和措置について解説します。
・よくある誤解3選
・対応しない場合のリスクと罰則
・個人事業主や中小企業の特例
これらの情報を正しく理解することで、過剰な対応を避けつつも法令遵守に必要な対応を適切に進めることができます。
それでは具体的な内容について、詳しく見ていきましょう。
よくある誤解3選
電子帳簿保存法について誤った解釈や認識が広がっており、これらを正しく理解することが適切な対応の第一歩となります。
法律名に「電子帳簿保存」とあるため「すべて電子化が必須」と誤解されがちであり、義務と任意が混同されて不要な負担を招くことがあるからです。
以下で、電子帳簿保存法に関するよくある誤解と事実を見ていきましょう。
| よくある誤解 | 事実 |
|---|---|
| 全ての帳簿・書類を電子化しなければならない | 義務化されているのは電子取引データの電子保存のみ 紙で受領した書類は紙のまま保存可能 電子帳簿等保存やスキャナ保存は任意の対応 |
| システム導入が必須である | 事務処理規程作成などシステム導入以外の方法でも対応可能 小規模事業者はファイル名のルール化や検索用台帳作成で対応できる 段階的な導入アプローチも許容される |
| 罰則はないので対応を後回しにしても良い | 青色申告の取り消しや重加算税の加重などのペナルティあり 税務調査の長期化や追加の資料提出を求められる可能性 取引先や金融機関からの信頼低下リスクあり |
電子帳簿保存法は全書類の電子化を義務付けるものではなく、電子取引データの電子保存のみが義務付けられています。
過剰な対応は避けつつ義務化部分については確実に対応し、任意部分は状況に応じて段階的に検討することが賢明な対応といえるでしょう。
対応しない場合のリスクと罰則
電子帳簿保存法に正しく対応していない場合、税務上の不利益や法的リスクが生じる可能性があります。
適正な記帳と保存は納税義務の基本であり、電子取引データの保存は2024年から完全義務化されているため違反に対してはペナルティがあります。
電子帳簿保存法への対応を怠るとどうなるのか、以下で見ていきましょう。
- 電子帳簿保存法に対応しなくても罰則はないの?
-
いいえ、以下のような罰則やリスクがあります。
- 青色申告の承認取消しの可能性
- 過少申告加算税の10%加重
- 法人税法違反で100万円以下の罰金
- 税務調査の長期化
- 青色申告の承認取消しとはどういうこと?
-
青色申告の特典(65万円の特別控除など)が受けられなくなり、税負担が増加します。
また、赤字の繰越控除なども利用できなくなります。
- 税務調査でどのような影響があるの?
-
適切に保存されていないと追加の資料提出を求められたり、調査が長期化したりする可能性があります。
また、過去の取引の証明が困難になり、経費性を否認されるリスクも高まります。
- うっかり対応し忘れてしまった場合も罰則の対象?
-
意図的な隠蔽や仮装がなければ、直ちに青色申告が取り消されることは少ないとされています。
ただし、法律上の義務であるためできるだけ早く対応することが重要です。
電子帳簿保存法への対応は形式的なものではなく、税務上の重要な義務として認識すべきです。
意図的な不正や隠蔽があった場合は厳しいペナルティが科される可能性があるため、不明点は専門家に相談して適切に対応するようにしましょう。
個人事業主や中小企業の特例
個人事業主や中小企業に対しては、電子帳簿保存法において様々な緩和措置や特例が設けられています。
大企業と比較してIT環境や人的リソースが限られる中小企業や個人事業主の負担を軽減し、現実的な対応を可能にするための配慮といえるでしょう。
中小企業や個人事業主向けの主な特例は、以下のとおりです。
| 特例の種類 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|
| 検索要件免除 | 売上高5,000万円以下の事業者 | 「取引年月日」「取引金額」「取引先」などによる検索機能が不要 ファイル名のルール化などの対応も不要 |
| 紙出力・整理保存特例 | すべての事業者 | 電子取引データを印刷して取引年月日や取引先ごとに整理 紙出力して保存していても検索要件が免除 電子データ自体は保存が必要 |
| 猶予措置 | 相当の理由がある事業者 | システム導入が間に合わない場合 業務の繁忙期で対応が難しい場合 電子データのダウンロード要請に応じられること 印刷した書面の提示・提出の求めに応じられること |
中小企業や個人事業主は、これらの特例を活用することで最小限のコストと労力で電子帳簿保存法に対応できます。
まずは義務化されている電子取引データ保存に対応し、段階的に他の区分への対応を検討していくのが現実的なアプローチでしょう。
【まとめ】電子帳簿保存法への対応はシステム活用がカギ
電子帳簿保存法は2024年1月から電子取引データ保存が完全義務化され、すべての事業者が対応を求められています。
本記事では基本から実践的な対応方法まで解説しましたが、適切な対応のポイントは自社に合った選択と段階的な導入です。
特に中小企業や個人事業主は特例措置を活用しながら、まずは義務化された電子取引データ保存に確実に対応すべきでしょう。
事務処理規程の整備やファイル名の工夫など初期コストを抑えた方法から始め、余裕があれば専用システムの導入を検討してください。
電子帳簿保存法は単なる法令遵守だけではなく、業務効率化やペーパーレス化を通じて企業のDXを推進する機会でもあります。
自社の状況に合わせた適切な対応で、法的リスクを回避しつつビジネス環境の最適化を目指しましょう。
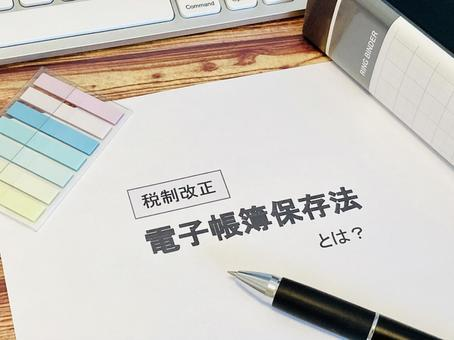

コメント